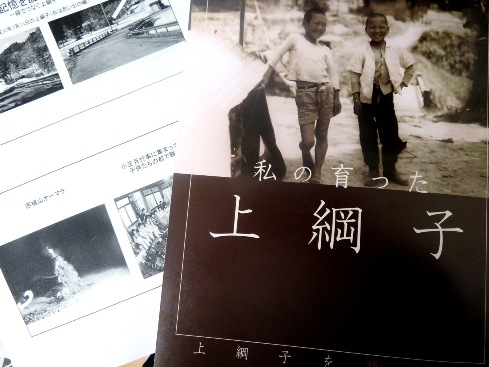今朝は風も収まり、暖かい陽射しがまぶしいくらいになっています。おはようございます。歩いて事務所に来る途中、ツクシを見つけました。雪もほぼ消えて、いよいよ本格的な春です。
昨日は午前が「しんぶん赤旗」日曜版の配達と集金でフル回転でした。と言っても、あまりにも美しい景色が北にも南にも見られ、写真撮影も忙しかったのですが。下の写真は柿崎区上金原で撮った米山さんとオオイヌノフグリです。

先日、『私の育った上綱子』という冊子が出来上がり、その記念講演会が市民プラザであるということを新聞で知りました。上綱子は私が育った旧吉川町尾神と似たような環境の山間地集落です。自分の生まれたところを深く知る助けになるにちがいない、そう思って昨日、参加してきました。参加した感想をひと言でいうならば、「面白くて、ためになった」ということになります。
講師は上越市専門学芸員の小島幸雄さん。講演のタイトルは「記憶を記録に!…縁でつなぐ上綱子…」。小島さんは、「遺跡にしても文化財にしても、そこにあるのは人間だ。上綱子の話をするというよりも、人間がどう生きてきて、何故つながりを持つのか、語りたい」と前置きして、1時間ほど講演しました。
講演では、今回の冊子に書いてあることや小島さん自身が仕事でかかわったことに時どき触れながら、西横山や上綱子の暮らしのことなどを面白く語られました。
例えば、「つとっこ」の話。私のところでは「つっとこ」というのですが、わらで作った「ごっつおの入れ物」のことです。お呼ばれしてご馳走になった「ごっつお」が残ると、それを「つとっこ」に入れて持ち帰る。ところが、酔っ払って「つとっこ」を振り回しているうちに中身がすっかりなくなってしまったこともあった、と言って笑わせました。
結婚式については、結婚を祝って、三日三晩、飲み続けた当時のことを語りました。新郎は何をしていたかというと、燗をしていたとのことです。これは、私の父もそうだったと聞いています。すでに遠い昔のことかと思ったら、講演会の会場の最前列に、三日三晩、祝いが続くという結婚式を経験したという男性がいました。もっとも、その「お婿さん」は「燗をする」役ではなく、飲み続けたそうですが。
冊子には「道」のことで、「車が通る前の道の思い出」などが2ページに渡って書かれています。小島さんは、「道は世の中を変えていってしまう。道は縁を解体する役割もする」とのべました。そして例に挙げたのは、鉄道の進歩です。一泊二日で文化庁へ出張した時に、「夕方5時に来るように言われたこともあったが、いまは日帰りになった」などと語りました。私は道の話を聞きながら、私が住んでいた尾神の、砂利もしいてない「べと道」のことを思い出していました。話を聴いた人たちは、私と同じように自分の思い出と重ね合わせていたのではないでしょうか。
講演で参考になったことがいくつかあります。その1つは、伝統行事を守るには続けることが大事だということ。たとえ、子どもの参加者がいなくなっても、地元関係者が組織を作り、周りの者が応援する仕組みを作って守っていく、再び子どもの参加が可能になったときには元の形に戻していく。「継続は力なり」という言葉が重く伝わりました。2つ目は記録の重要性です。冊子の中で、「金剛畑で土器が出た」ことが書いてありますが、こうした記録があるからこそ、誰かが読んでくれる、という話がありました。ごく当たり前のことではありますが、私としては、いま書き続けている随想、「春よ来い」にも通じることなので、書き続ける励ましにもなりました。最後にもう一つ、小島さんの講演の準備はやはりすごい。最初に書いた「つとっこ」の話をするために、実物より少し小さめのものを持参されていました。たぶん、自分で作られたものだと思います。そして、昨日の朝は、「上綱子」を訪問して、レジュメにそのときの写真を3枚掲載されたのです。元々、知識も豊富で、話し上手の人でもここまで準備しているとはびっくりでした。
小島さんの講演を聴くのは今回で5回目くらいかと思います。今回、初めて知ったことがありました。小島さんは、富山市役所時代に濱谷浩の写真集、『裏日本』と出合い、『雪国』を知ることになったとのことでしたが、じつは私もそうだったのです。新潟大学の古厩忠夫教授(故人)の『裏日本』(岩波新書)を読み、同じタイトルの写真集が高田図書館にあることを知り、それをきっかけに桑取谷を取材した写真集、『雪国』にたどり着いたのです。もうひとつ、小島さんが最初に遺跡の発掘をしたときにお世話になった人が柿崎の室岡博さん(故人)だったということも初耳でした。室岡さんは私が長年、お世話になった中村三代志先生と兄弟の関係です。なにか縁を感じます。
講演会が終わってから、1階で行われていた蘭の展示会を観てきました。色とりどりの欄が咲いている会場、春蘭の会の展示会場、2つとも観て、楽しませてもらいました。春蘭の会場では小林元教育長や吉川出身の橋爪進さんと会い、ゆっくり話をすることができました。
活動レポート1850号、「春よ来い」の第498回、「雪に耐えて」を私のホームページに掲載しました。ご笑覧ください。
きょうは午前にデスクワークをし、午後から高田に向かいます。